貸株って何ですか?
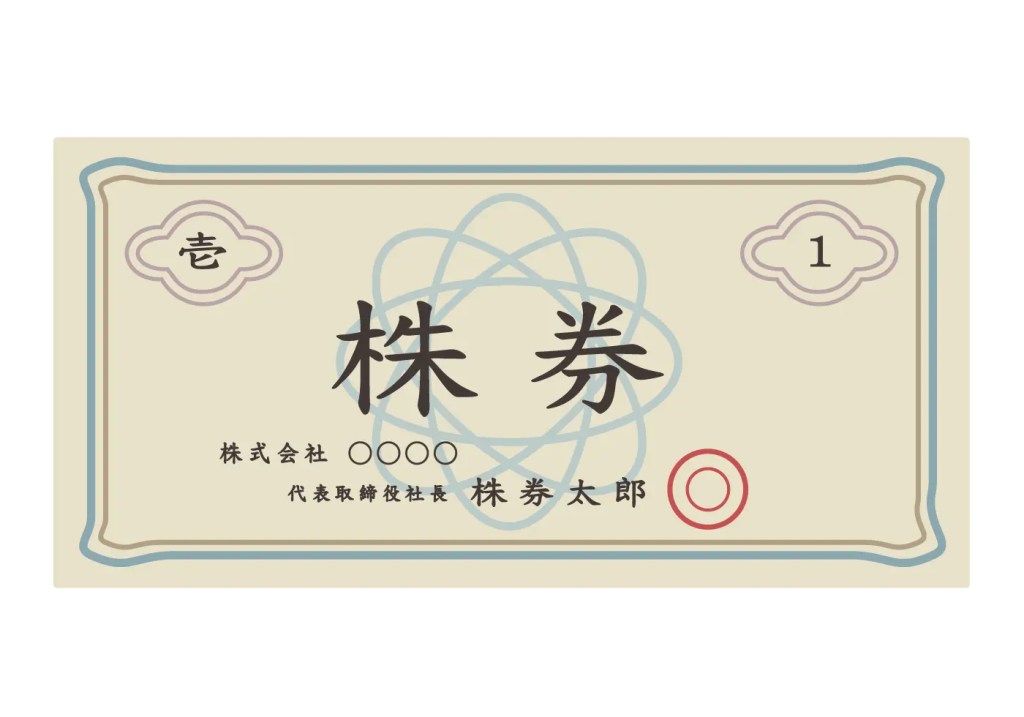
「貸株(かしかぶ)」とは、投資家が保有している株式を証券会社に貸し出すことで、貸した株式に応じて「貸株料(貸株金利)」という形で金利収入を得られるサービスです。
証券会社は投資家から借りた株を空売りを行いたい投資家などに再度貸し出すなどして収益を得ています。
貸株サービスは、長期保有を基本とする投資家にとって、株式を売却することなく追加の収益を得られる手段として注目されています。
目次
1 貸株の仕組み
(1)登場人物とそれぞれの役割
①貸し手:投資家
証券口座で貸株サービスを申し込み、保有株を証券会社に貸し出す。
貸出期間中は株の所有権は保有したままで、株のレンタル料である「貸株料」を受け取る。
②借り手:主に機関投資家や空売り投資家
証券会社から株を借り、株式市場で空売りを行うなどに活用する。
③証券会社
投資家から株を借り受けて、借り手に転貸する。
借り手から得た貸株料の一部を貸し手に還元する形で収益をシェアする。
(2)貸株の貸出期間
貸株サービスは、多くの証券会社では「自動更新」になっている場合が多く、投資家が解約を申し出ない限り、毎日自動的に貸株状態が更新されます。
投資家が株を売却した場合には、その時点で貸株は終了します。
(3)貸株料(貸株金利)の仕組み
貸株料は、貸し出した株の時価評価額に年率換算の貸株金利をかけ、日割り計算されます。
たとえば、ある株の貸株金利が年1.0%であれば、100万円分の株を1年間貸し出すと理論上は年間1万円程度の貸株料収入が得られる計算です。ただし、実際には日数・株価変動などで前後します。
貸株金利は、株式の需給状況や証券会社の方針により銘柄ごとに異なり、一般的に人気の低い銘柄は貸株金利が低めに、空売り需要が高い銘柄は貸株金利が高めに設定される傾向があります。
2 貸株のメリット・デメリット
(1)メリット
①追加収入を得られる
長期で株を保有している場合、株を手放すことなく、配当や株主優待に加えて貸株料を得られます。
②資金効率の向上
銘柄を保有しているだけで収益源が増えるため、資産運用効率が向上します。
③原則としていつでも売却可能
貸株中であっても、投資家が売却注文を出せば通常通り売却が可能であるため、貸株サービスによって株式の売買は妨げられることはありません。
④特別な手続きが不要
貸株サービスは一度申し込めば、あとは自動で貸株状態が更新されるので余計な手間がかかりません。
(2)貸株のデメリット・注意点
①配当との関係
配当についても、貸株中に配当権利日を迎えた場合、証券会社から「配当金相当額」として支払われます。
これは本来の配当金と同額ですが、税務上「配当所得」ではなく「雑所得」となるため、配当控除が適用できず、課税額が増える可能性があります。
②株主優待との関係
貸株中は株式の所有権は保有していても、名義が証券会社になるため、継続保有特典付きの株主優待銘柄などは株主優待の権利が得られません。
このような銘柄は貸株に出さないほうが無難です。ただし、証券会社によっては「株主優待優先モード」や「権利確定日自動返却モード」などを用意している場合があり、この場合には権利確定日に自動的に株を投資家名義に戻してくれます。
③貸株料は変動する
貸株金利は証券会社の判断で変更されるため、将来も同じ利回りが続く保証はありません。
④株主優待銘柄
株主優待銘柄のなかには、継続保有特典付きの株主優待銘柄があります。
この銘柄を貸株に出した場合、継続保有特典が失われ株主優待を受け取ることができなくなります。
⑤NISA口座内の株式
特定口座や一般口座で保有している上場株式等は貸株に出すことができますが、 NISA 口座で保有している上場株式等は貸株に出すことができません。
⑥信用リスク(証券会社のリスク)
貸し出している株式等は、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
したがって、証券会社が破綻した場合、貸し出している株式が返還されないリスクがあります。
3 貸株に向いている人・向かない人
(1)貸株に向いている投資家
・長期保有が前提で、売却予定のない株を多く持っている投資家
・株主優待や議決権へのこだわりがない、または株主優待優先モードでカバーできる人
・配当控除が不要・適用を気にしない人
・短期売買が少なく、株式を保有し続ける期間が長い人
(2)貸株に向いていない投資家
・株主優待の取得を重視している人(モードを設定できない証券会社を使っている場合)
・配当控除を最大限活用したい人
・議決権行使を通じて株主として企業経営に意見を伝えたい人
4 貸株の始め方
貸株サービスはSBI証券、楽天証券、マネックス証券など多くのネット証券が提供しています。
証券会社によってサービス内容やモード設定の柔軟性、貸株金利に差があるので、貸株を始める前に必ず確認しましょう。
貸株は、以下の流れで始めることができます。
①貸株サービスを提供している証券会社に口座を開設する。
②貸株サービスに申し込む(ネット証券であればWebから簡単に申込み可)。
③貸株対象銘柄を証券口座に保有する。
④貸株金利や貸株設定方法(自動貸出・優待優先モードなど)を選択する。
⑤貸株開始後は毎月(または毎日)貸株料が口座に入金される。
5 貸株の税金
貸株料は、所得税等の「雑所得」に区分されます。
雑所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して所得税・住民税が課税されます。
年間20万円以上の雑所得がある場合は確定申告が必要になるため、貸株料収入が大きい場合は注意が必要です。
また、配当金相当額も雑所得として課税され、配当控除を受けられないため、貸株中の配当は税務上の扱いが通常の配当金と異なります。
6 貸株サービスのモード設定
多くの証券会社では、以下のようなモード設定を選択できます。
モード選択を誤ると、配当控除が受けられなくなる、株主優待を取り逃がすなどのトラブルにつながるため、自分の投資方針に合わせたモード設定が重要です。
①金利優先モード
権利確定日を気にせず貸株を続け、最大限貸株料を受け取るモード
②株主優待優先モード
権利確定日に自動的に貸株を返却し、優待権利を確保するモード
③配当優先モード
配当権利日に貸株を返却し、配当金を「配当所得」として受け取るモード
7 貸株を行うための確認事項
①モード設定を確認する
優待や配当を受け取りたい場合は、自分が利用する証券会社のサービス内容を理解し、モードを正しく設定する。
②金利変動をチェックする
銘柄ごとの貸株金利は流動的なので、定期的に見直しを行い、期待収益とリスクを把握する。
③証券会社の信用状況に留意する
破綻するリスクがある証券会社であるか否かを確認する。
④配当控除を受けられないリスク
配当金相当額は雑所得扱いになるため、配当控除による節税効果を失うリスクがある点を理解しておく。
8 まとめ
貸株サービスは、株式を長期保有する投資家にとって非常に魅力的な追加収入の手段です。
特に高金利の貸株料が付く銘柄を保有している場合、年間で数千円から数万円の収益になることもあります。
一方で、株主優待や配当控除が受けられないなどのデメリットも存在するため、自身の投資目的と税務面の影響を踏まえたうえで活用することが重要です。
証券会社ごとにサービス内容は異なり、金利設定や優待優先モードの有無なども差があるため、貸株サービスを始める際には各社の条件を比較検討し、自分に合った証券会社を選ぶことをおすすめします。

