インフレの時にはどのように運用したらいいですか?
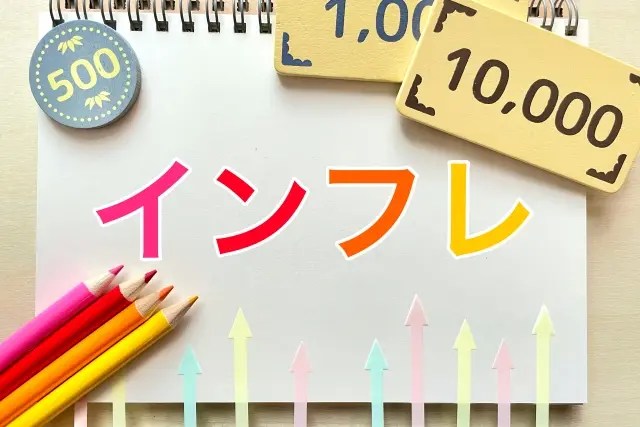
私たちの生活に欠かせない「お金」は、数字としては変わらなくても、その価値は経済環境によって大きく変わっていきます。
スーパーで買う食料品の値段が少しずつ上がったり、光熱費がじわじわ高くなったりすると、「あれ、同じ収入でも生活が苦しくなってきたな」と感じることがあるのではないでしょうか。
これこそが「インフレーション」、いわゆる物価上昇の影響です。
インフレは私たちの財布に直接響きますが、同時に投資を通じて資産を守り、育てるための大切なテーマでもあります。
なぜなら、ただ預金に置いておくだけではお金の価値が目減りしてしまうからです。
逆に、インフレの特徴を理解し、上手に活用することで資産形成のチャンスにつなげることもできます。
このコラムでは、インフレやデフレ、さらにはスタグフレーションといった経済の基本概念を整理しながら、インフレ時に個人投資家がどのように行動すべきかを一緒に考えていきましょう。
目次
1 いまさら聞けないインフレ
「インフレーション(インフレ)」とは、一般的に物価が継続的に上昇する現象を指します。
たとえば、日常的に買う食料品や生活必需品の価格が徐々に上がっていき、同じ金額では以前より少ないものしか購入できなくなる状態です。
インフレが進むと、通貨の購買力は下がります。
100円で買えたものが将来は120円になってしまうため、実質的にお金の価値が減ってしまうのです。
インフレにはさまざまな原因があります。
需要が供給を上回ることで生じる「需要インフレ」、原材料や人件費の上昇が価格に転嫁される「コストプッシュインフレ」、そして通貨供給量の増加による「マネーインフレ」などが代表的です。
経済が健全に成長している局面では適度なインフレは望ましいとされますが、過度に進むと生活コストが急騰し、家計や企業活動に大きな負担となります。
個人投資家にとってインフレは、自分の資産価値を守るうえで無視できない重要な要因です。
単に預金をしているだけでは購買力が減少し、実質的に資産が目減りしていくからです。
2 インフレ局面で投資するメリット
インフレは生活者にとって負担となる一方、投資家にとってはチャンスともなります。
物価上昇局面では、価格転嫁ができる企業の売上や利益が拡大しやすく、株価上昇につながるからです。
特に、生活必需品やエネルギー関連、資源価格の上昇に恩恵を受ける企業はインフレ局面で強みを発揮します。
また、インフレ時には「現金の価値が目減りする」ため、資金を実物資産や株式に移す投資家が増えます。
これが資産価格の押し上げ要因となることもあります。
たとえば、不動産や金(ゴールド)などはインフレに対するヘッジ手段として古くから利用されてきました。
つまり、インフレは「現金を持ち続けると損をする環境」でもありますが、同時に「うまく投資すれば資産を増やせる環境」でもあるのです。
3 インフレ局面での有効な株式投資法
インフレ環境における株式投資のポイントは、価格転嫁力と資産性に注目することが有効です。
① 価格転嫁力のある企業
インフレでコストが上昇しても、販売価格に反映しやすい企業は利益を維持することができます。
食品メーカーや日用品大手、電力・ガスなどの公益企業がその典型です。
② 資源関連株
原油、天然ガス、金属など資源価格の上昇はインフレ要因そのものです。
そのため、資源開発企業や商社は恩恵を受けやすくなります。
③ 金融株
金利上昇を伴うインフレ局面では、銀行などの金融株が有利になる場合があります。
貸出金利の上昇が収益改善につながるからです。
④ 高配当株
物価上昇で生活コストが増す中、安定した配当収入は投資家に安心感を与えます。
インフレ局面では「インカムゲイン」を確保することも重要です。
⑤ インデックス投資の継続
個別株選びが難しい場合、幅広い銘柄に分散投資できる株式インデックスファンドへの投資を継続するのも有効な方法です。
長期的に見れば、株式市場の相場全体がインフレの影響を受け、底堅い値動きをするからです。
4 インフレ局面での株式以外の有効な投資法
株式以外にも、インフレ対策として有効な投資先があります。
① 不動産
インフレ局面では土地や建物の価格が上昇しやすく、賃料も上がる傾向があります。不動産は実物資産であるため、インフレヘッジとして有効です。
② 金(ゴールド)
金は世界的に「価値保存の手段」として認知されています。
インフレや通貨不安が高まると資金が金に流れやすく、価格が上昇します。
③ コモディティ(商品)
原油や穀物、金属などの商品価格はインフレと連動しやすい特徴があります。
個人投資家でも商品先物やETFを通じて投資することができます。
④ インフレ連動国債
物価変動率に応じて元本や利息が増減する仕組みの国債です。
日本でも「物価連動国債」が存在し、インフレ時には元本、利息とも増えるので、インフレ対策として利用できます。
⑤ 外貨建て資産
円安を伴うインフレ局面では、外貨建ての株式や債券、外貨預金などを持つことでリスク分散になります。
5 インフレ時の投資での注意点
インフレ時の投資には大きなチャンスがある一方、いくつかの見過ごせないリスクもあります。
「インフレだから投資すれば儲かる」と単純に考えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることもあるのです。
ここでは、インフレ局面で投資を行う際に特に注意すべきポイントを整理してみましょう。
(1)過度なリスクを取らない
まず大切なのは、「インフレ=資産価格の上昇」という思い込みを捨てることです。
確かに、インフレは株式や不動産、金などにとってプラス要因となる場合があります。
しかし、それはあくまで一部の局面に限られます。
たとえば、インフレが加速すると政府や中央銀行は物価を抑えるために政策金利を引き上げることがあります。
金利が上がると企業の借入コストが増加し、設備投資や消費が冷え込みます。結果的に企業収益が悪化し、株価が下落する可能性もあるのです。
不動産も同様で、金利上昇により住宅ローンや不動産投資ローンの負担が増し、買い手が減少すれば価格は下がりかねません。
つまり、「インフレだから安心」とは言えず、むしろ金融政策や景気動向によって逆風となるリスクも抱えているのです。
投資判断を下す際には、インフレという一要素だけでなく、金利や景気サイクル、政策対応など幅広い視点から状況を見極めることが不可欠です。
(2)分散投資を徹底する
インフレ局面においても、投資の基本原則は変わりません。
それは「分散投資」です。特定の資産に集中すると、予想外の変動が起きたときに損失を大きくしてしまいます。
たとえば、株式市場が好調でも、突発的な世界的景気後退や政策変更によって一気に下落することがあります。
不動産についても、地域や物件種別によって値動きが異なり、全体が必ず上昇するとは限りません。
金や原油といったコモディティも価格変動が激しく、短期的には大きな下落リスクを伴います。
こうしたリスクを抑えるためには、株式、不動産、金など複数の資産クラスに分けて投資することが重要です。
資産クラスごとに値動きの要因が異なるため、一方が下落しても他方がカバーしてくれる可能性があります。いわゆる「卵は一つのカゴに盛るな」という格言は、インフレ下においても有効なのです。
さらに分散は資産種類だけでなく、地域や通貨にも広げることが望ましいでしょう。
日本国内だけに投資を集中すると、円安や国内景気の影響を強く受けてしまいます。
米国や新興国市場の株式・債券などを組み合わせれば、世界経済全体の成長を取り込むことができます。
(3)長期的視点を持つ
インフレ時の市場は短期的に大きく揺れ動くことがしばしばあります。
物価の変動はニュースや統計データに敏感に反応し、株価や為替は大きく上下します。
そのため、短期的な値動きに翻弄されて頻繁に売買を繰り返すと、むしろ損失を増やしてしまう危険性が高いのです。
資産形成を目的とするなら、インフレ対策も「長期投資」を前提にすることが効果的です。
たとえば、株式市場全体は、長い目で見るとインフレを上回るリターンを生み出してきました。
一時的に相場が下落しても、時間を味方につけて投資を継続すれば、トータルでの成果はプラスになる可能性が高いのです。
また、長期投資を続けることで「複利の力」を活用できます。
得られた配当や利息を再投資すれば、資産は時間とともに雪だるま式に増えていきます。
インフレは時間とともに資産を目減りさせますが、長期的な投資はその影響を吸収し、資産を増やす原動力となるのです。
(4)自分のリスク許容度を確認する
最後に忘れてはならないのが、自分自身の「リスク許容度」をしっかりと把握することです。
インフレ対策だからといって、必ずしもリスク資産を多めに持たなければならないわけではありません。
投資家一人ひとりの状況は異なります。年齢や収入、資産規模、家族構成、将来のライフプランによって、取れるリスクの度合いは大きく変わってきます。
たとえば、定年を控えた人が生活費の大半を投資に回すのは危険です。
逆に若い世代であれば、多少の値動きリスクを受け入れて長期的な成長資産に投じる方が合理的かもしれません。
また、投資はあくまで「余裕資金」で行うことが前提です。
日々の生活費や将来必要となる教育資金、住宅資金などを無理に投資に回してしまうと、相場の変動で生活が圧迫される危険性があります。
インフレ対策を考えるときも、まずは生活基盤を守ることを最優先にすべきです。
自分のリスク許容度を正しく把握すれば、精神的にも安定して投資を続けることができます。
「損失が出ても夜眠れない」という状況は長続きしません。
安心して続けられる投資スタイルこそが、インフレ対策においても長期的な成功につながります。
6 まとめ
インフレーションは資産形成において無視できない重要なテーマです。
物価が上昇すると現金の価値は目減りし、資産が実質的に減少してしまいます。
しかし、投資を通じてインフレを味方につけることも可能です。
多様な資産クラスを上手に組み合わせることで、インフレ環境に強いポートフォリオを構築できます。
一方で、インフレ局面は不確実性も高いため、過信は禁物です。
分散投資を基本とし、自身のリスク許容度に合わせて投資スタイルを選ぶことが重要です。
長期的な視点を持ちながら、経済環境の変化に柔軟に対応していくことが、インフレ時代を乗り切るカギとなるでしょう。

