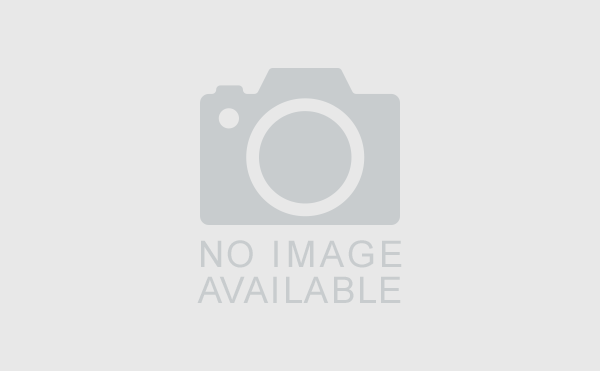自分のことを知ることから始めよう!

証券口座を開設したものの、その後どうすればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
資産運用には基本的なルールがありますが、目的や好みは人それぞれ異なるため、具体的な方法も一様ではありません。
そのため、投資初心者が迷ってしまうのも当然です。
そこで、本コラムでは、皆さんが資産運用を始める前に確認しておくこと、注意しておくことなどについて、解説していきたいと思います。
これによって、ご自身の資産運用の方向性が明確になり、効率的かつ効果的に資産を増やすことができるのではないかと思います。
目次 [非表示]
1 資産運用を始める前にやるべき5つのステップ
ステップ1: 手持ちのお金を仕分けしよう
まずは、手持ちのお金を「用途別」に仕分けすることが重要です。資産運用の基本は、リスク管理を意識しながら資産を分散することにあります。この際、以下の3つの用途に分けて考えましょう。
① 生活資金+緊急用資金
日常の生活費や突発的な出費(病気やケガ、冠婚葬祭、失業など)に備えるためのお金です。
一般に生活費の3~6か月分が目安とされています。
これらの資金は高い流動性と安全性を重視するため、元本保証があり、即時に引き出せる普通預金や証券口座のMRF(マネーリザーブファンド)などを利用することが推奨されます。
② 使用予定資金
住宅購入の頭金や子どもの教育費など、5~10年以内に利用する予定のある資金です。
中期的な運用を想定するため、ローリスク・ローリターンの運用が基本となります。
③ 余裕資金
しばらく使用する予定がなく、長期間にわたり運用できる資金です。長期運用を前提にすることで、リスクを取ることでリターンを高める戦略が有効になります。
ステップ2: 投資の目的・期間・目標金額を明確にしよう
投資において、明確な目標設定は極めて重要です。
例えば、「20年後の老後資金を準備する」「5年後に住宅購入の頭金を確保する」など、具体的な目的を設定することで投資計画を立案しやすくなります。
また、必要な金額や達成までの期間を設定することで、年間の期待リターンを逆算し、適切なポートフォリオを構築する指針となります。
ステップ3: 投資できる金額を確認しよう
投資に充てられる資金の確認は、ステップ1で仕分けた「余裕資金」がどれだけあるかを基準に判断します。
例えば、300万円の余裕資金があり、毎月1万円を10年間、さらに10年後からは毎月3万円を追加投資する計画など、具体的な資金配分を考えましょう。
ステップ4: リスク許容度を確認しよう
自分のリスク許容度を理解することも重要です。リスク許容度は、以下の4つの要素で評価されます。
① 性格:価格が下落しても冷静に判断できる人は、リスク許容度が高くなります。
② 年齢:若いほど投資期間を長く取れるため、リスク許容度が高くなる傾向があります。
③ 知識・経験:経済や金融市場に関する知識が豊富であるほど、リスクを理解し、適切に対処できる能力が高まります。
④ 資産規模:保有資産の規模が大きいほど、一部の損失に対する許容度も高くなります。
ステップ5: 自分に合う投資商品を選ぼう
自分のリスク許容度や投資目標に合った商品を選ぶことが重要です。
一般的に、リスクとリターンの関係は次のようになります。
預貯金 < 国内債券 < 海外債券 < 国内株式 < 海外株式
さらに、株式や債券には個別銘柄のほかに、投資信託やETF(上場投資信託)といった分散投資を可能にする商品も存在します。特にインデックスファンドやアクティブファンドは投資初心者にも有効な選択肢です。
2 資産運用での注意点
注意点としては、分散投資の重要性と資金の余力を持たせることです。
分散投資によりリスクを軽減し、余力資金を確保することで、相場下落時に追加購入を行う柔軟性を確保できます。
投資を行う際は、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で安定的に資産を増やすことを目指しましょう。市場の変動に一喜一憂せず、継続的に資産運用を行うことが重要です。
3 資産運用資金の作り方
資産運用の世界において、「余裕資金で投資を行うこと」は鉄則とされています。
しかし、「お金を増やしたいが、そもそも余裕資金がない」という悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
ここでは、資産運用資金を作るための方法についてご紹介します。
(1) 家計の見直し
収入が大きく増えない環境下で資産形成を図る際に、まず取り組むべきは支出の最適化です。
支出を効率的に削減することで、余裕資金を捻出することができます。
① 支出の見える化
家計簿アプリやエクセルを活用し、1か月間の支出を詳細に把握しましょう。
特に、変動費(食費、娯楽費など)と固定費(家賃、通信費など)の区別を明確にすることが重要です。
支出を可視化することで、無駄な出費や削減可能な支出を見つけやすくなります。
② 固定費の見直し
固定費には住居費、通信費、保険料、教育費、自動車維持費などが含まれます。
特に保険料や通信費は見直しの余地が大きい項目です。
保険であれば必要最低限の保障内容に変更する、通信費であればプランの見直しや格安SIMへの乗り換えを検討することが有効です。
③ 変動費の見直し
食費や日用品費、交際費、趣味・旅行費用などは、無理のない範囲で削減を検討しましょう。
例えば、外食の回数を減らす、サブスクサービスを見直すなどの工夫が考えられます。節約はストレスにならない範囲で行い、楽しみを完全に断たないことも大切です。
(2)積立による生活費3か月分の確保
資産運用を始める前に、まずは生活費3か月分の貯蓄を目標に積み立てを行いましょう。
これは突発的な支出に備えるためのセーフティネットとして機能し、精神的な安定をもたらします。積み立てを自動化することで、無意識のうちに資金を蓄えることができます。
(3) 積立による投資信託購入の開始
生活費3か月分の貯蓄が確保できたら、次のステップとして定期的な投資を始めましょう。
証券口座には投資信託を自動で定額購入できるサービスが提供されていることが多いため、これを利用することで時間を分散した投資が可能になります。
例えば、毎月1万円を年利5%で10年間積み立てると、最終的には約155万円になります(元本120万円、運用収益35万円)。特に全世界株式インデックスファンドなど、分散投資ができる商品を選ぶことが推奨されます。
4 まとめ
投資初心者にとって、「余裕資金の確保」は大きなハードルに感じられるかもしれません。
しかし、家計を見直し、無理のない範囲で積み立てを行うことで資金を捻出することは可能です。
また、投資を始める際は少額から始めることが重要です。市場の変動に一喜一憂せず、コツコツと継続することが将来的な資産形成につながります。
ぜひ、自分に合った方法で資産運用を始めてみましょう。